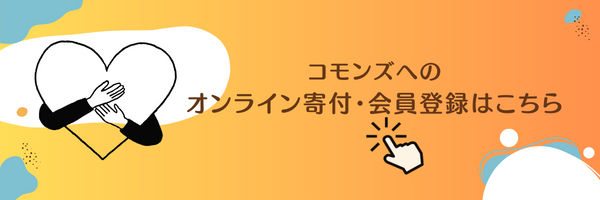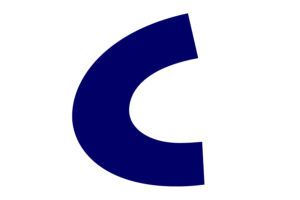すべての子どもたちが学ぶ機会を得られる未来を紡ぐ新しい場づくりに取り組みます
赤い羽根福祉基金 2025年度事業助成の新規事業で助成決定しました。「すべての子が学ぶ機会を得られる未来を紡ぐ教室を多様な主体の協力で作り出す事業」を事業名に掲げ、新しい場づくりに取り組んでいきます。
事業概要
本事業はスリランカ、バングラディッシュ、パキスタンなどから来日した家族で、在 留資格や宗教的背景、来日年齢により小中高での教育が受けられない、または入れても退学してしまう 子どもが多い現状に対して 県内の学習支援団体、教育行政、外国籍コミュニティが課題を共有し、3 者の協力によって適切な教育の 機会、新たな教育の場をつくり、誰もが日本で学ぶ権利と社会の一員となる権利を保障する地域をつくっていくことを目指します。
対象地域
茨城県全域
重点エリアは「県南・県西エリア」
活動の背景・課題認識
コロナ禍の入国規制が解除されてから南アジア(スリランカやバングラディッシュ等)から来日し、難民申請している家族の子どもの住民票がないなどの理由で、小中学校に就学しにくい状況がおきています。
そうした家族は就労もできず家賃や学費、生活費でも苦労し、医療保険に入らないと病院にも行けない状況です。そのため、第1の課題は難民申請中でも就学できるようにすることです。住民登録している子どもでも、公立学校に在籍せず就学状況が不明な子が、県内には一定数いますが、その実態把握が進んでいない現状です。
また、タリバン的発想などにより女子が就学できないケースがあります。義務教育年齢の外国ルーツの子どもの不就学の実態把握と就学支援が第2の課題となります。 日本の成人年齢が 18 歳となり 16,17 歳で来日する子どもも増えています。年齢的に日本の中学校に入れない状況で高校受検を希望しても、日本語力も乏しく受検の手続きも支援が必要な状況です。
茨城県教育委員会は外国籍生徒を重点的に受け入れる高校を設けていますが、高校に入学しても授業についていけず退学する生徒も少なくありません。日本の中学校を経ずに高校受検するオーバーエイジの子どもが高校教育にアクセスできるようにすることが第3の課題です。
こうした重点受け入れ校や公立の夜間中学校は、県西地域にしかありません。そのため、その他の地域の子どもが入れる環境の整った教育機関がないのが第4の課題となります。
これまで主な学習支援の対象であった日系ブラジル、フィリピン人の多くが日本生まれになってきました。最近学校に増えてきているスリランカやバングラディッシュ、パキスタンなどから来た保護者の中には、保護者が就労ビザで、子どもが家族滞在ビザの場合が多い印象です。このような子どもは、日本語力が乏しい上に高校を卒業しないと週 40 時間働けるビザに変更することができないのです。こうした子どもが日本社会で生きていくには、学校に入る前の日本語初期指導の体制づくりと、高校に入ったあとに卒業し地域でキャリアを作っていくのを支援する体制を作る必要があります。これが第5の課題です。
当会は、15 年前から外国ルーツの子の就学や高校進学支援活動を行い、2018年から、県教育委員会 から小中高に在籍する児童生徒への日本語指導、保護者面談の通訳派遣、文書の翻訳などを受託し取り組んできました。 けれども上記1から5の課題は就学前の課題であり、これまで十分に検討されてきませんでした。
これらの問題解決のために、県内外で外国ルーツの子の支援を行っている団体や機関、そして、子どもの親が属する外国籍コミュニティとネットワークを構築しながら、5つの課題を克服することに取り組んでいきます。
活動の目標(5つの課題)
- 難民申請中の家庭の子の就学や就学援助、国民健康保険申請手引きが完成普及
- 県内全自治体で外国籍児童の不就学実態調査が実施され必要な就学支援も実施
- オーバーエイジ向け日本語指導プログラムが県内複数個所とオンラインで実施され、指導について 一部公費負担も行われている。
- 県西以外に公立夜間中を設置するための検討がスタートしている。
- 県内の複数の市教委がプレクラスの予算をつけ初期指導の体制づくりが進んでいる 就学、進学支援を推進する組織として、外国ルーツの子を支援する人や組織によるネットワークができ、他県 とも連携し県内自治体への提言を行う会議体が実現
第1年次の達成目標
- 県内で外国ルーツの子にかかわるボランティア、スクールソーシャルワーカーなどがネットワークに 20 名以上 参画し、情報交換会が定期的に開催される。
- メンバー向けの研修が行われ、各種支援ツールが共有される。
- 難民申請中の家族、仮放免の家族でこどもが就学、進学を希望した際にどう支援すればいいかの手引きを作成し ネットワーク関係者,県内教育委員会に配布するほか WEB に掲載する。
- 県教育委員会と県西地域の市町村教育委員会との懇談会が開催され、不就学、日本語初期指導、夜間中や重点受 け入れ高校の増設の必要性に関する意見交換、ムスリムコミュニティとの協力などに関する協議が行われる。
- オーバーエイジ向けオンライン学習、民間によるプレクラスが施行される。
第1年次の活動内容及びスケジュール
- 外国ルーツの子に関する市民団体、国際交流協会、協力隊 OV ,訪問型家庭支援員、スクールソーシャルワーカー などに、教育支援ネットワーク(仮称)への参加よびかけ(4~6 月)
- 隔月の情報交換会、支援ケース検討会、をハイブリット型で実施。(年間通して)
- ネットワークメンバー向けセミナーを 5 回実施(テーマ案:不就学対応、オーバーエイジ対応、難民申請中の 家族対応、プレクラス、夜間中設置運動(6~9月予定)
- 愛知県などでのプレクラス、不就学状況把握、夜間中設置運動の視察の実施(6~10月)
- ムスリムコミュニティリーダーと東京や名古屋などにあるイスラム学校の視察(7・8月)
- 県ならびに県西地域の市町村教育委員会とネットワークの懇談会の企画開催(9~11月)
- 難民申請中等要配慮世帯の子への就学・進学支援に関する手引き、事例集作成(8月までを予定)
- オーバーエイジ向け受検支援を県内各地に横展開(10 月~26年2月)
- プレクラスと公立夜間中増設に関するキャンペーン準備(10 月~26年3月)
推進体制
- ネットワーク運営(情報交換、セミナー) ネットワーク構成団体に参加と協力を依頼
- 外国籍家族向け相談支援 各エリアの団体が行うのをコモンズが資料提供などで後方支援
- 教育委員会懇談会 ネットワーク世話役とコモンズで会議開催、記録
- コミュニティとの懇談 ネットワークのキーパーソンとコモンズで企画運営
- 不就学をなくすためのキャンペーン 資料作成はコモンズ 啓発はネットワークで協力
- 不就学実態調査 まず自治体に実施を呼びかけ、実施する場合、ネットワークを通じて 調査協力者を募集
- プレクラス試行 日本語初期指導希望者を募り、ニーズが出た際にマッチング
- オーバーエイジ向け学習 コモンズは継続事業として実施、他団体にも実施呼びかけ

この事業は、コモンズだけではなく、多くの皆さまのご協力、ご支援が必要です。引き続き、日本語や学習支援のボランティアなどご協力をいただきたくお願いいたします。
◆ 本件に関するお問い合わせ
認定NPO法人 茨城NPOセンター・コモンズ
代表理事 横田 能洋
〒303-0003
茨城県常総市水海道橋本町3571 えんがわハウス内
(関東鉄道常総線「北水海道駅」より徒歩7分)
電話:0297-44-4281
FAX:0297-44-7291
eメール:info@npocommons.org